|
|
||
|
その日の皇居周辺は、皇太子と雅子さんの結婚の儀を翌日に控えていたこともあって、まるで戒厳令でもひかれたように、警官や機動隊であふれかえっていた。
|
|||
 |
|||
|
地下鉄の切符を買っていると、後ろから人差し指でつつかれ、振り返る。
|
|||
 |
|||
平日の昼下がりの美術館は、入場者も少なく、ひっそりと静まりかえっていた。妙齢のご婦人たちや初老のカップル、見るからに美術館巡りが好きそうな女の子ぐらいしか見かけることはなかった。 孤高の版画家といわれた長谷川潔の、デッサンや油絵、木版などが数多く展示されている展覧会で、なかでも印象的なのは銅版画だった。メニエル・ノワールという技法によって出された黒が、本来は単調な色にもかかわらず、じつに色彩豊かなものに感じられる。彩りの豊かな油絵のほうが、不思議なことに単調に見えてくるほどで、とくに銅版画「飼い馴らされた小鳥」では、ガラス器やその中に入っている水が、どこまでも透き通っていて、黒の濃淡だけで、よくこれほどまで表現できるものだと驚かされる。 一時間ぐらいかけて見てまわり、ミュージアムに行ってカタログを買い、最後にもう一度、気になった版画の前に立ってしばらく過ごし、それから広々とした庭に出てみる。 喉が乾いたので、喫茶室でコーヒーを飲みながら展覧会のカタログを読み、読み終わって帰ろうとすると、何か忘れ物をしたような気分に襲われる。そのまま立ち去りがたく、庭に戻り、ベンチに腰を下ろす。 見上げると空には、厚い雲がたれ込めていた。それでも六月に入ったからか、木々の緑が深く、鮮やかだった。 はっきりしない天候のため、庭園には人影も疎らで、葉と葉の擦れ合う音や、鳥のさえずり、乳母車に語りかける母親の声などが、どこからともなく聞こえてくるばかりだった。 しばらく、静かな時間の流れに身を任せていると、やがて何を忘れていたかが思い出される。ポケットにしまってあった指名リストを取り出し、自分が指名しようとする馬を確認しながら、何頭かの名前の横にクエッションマークをつけ、何頭かの名前を消す。
|
|||
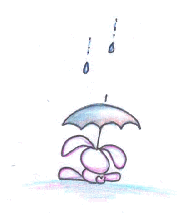 |
|||
四時過ぎにオフィスに戻り、二、三本電話をかけ、新聞を読んでいるうちに終業時間を迎える。外に出ると、自然と足は、神楽坂の居酒屋「もきち」へと向いていた。 テレビと週刊誌で紹介され続けたせいか、最近は一段とお客さんの出足は早く、六時を過ぎると人数によっては席がないことあって、残念そうに入り口で帰っていく客も少なくなかった。 いつもの席につき、いつものようにお店の人と話しながら、いつもの酒を呑んでいく。 お客に競馬好きの多いこの店では、春にはクラシック・レースでおおいに盛り上がるが、六月の声を聞くと話題は一変する。ダービーやオークスは、すでに昔の物語となり、すべては数日後に開かれるペーパーオーナーゲームの指名馬選択会議に集中する。 ペーパーオーナーゲーム、通称POGは、出走前の三歳馬を選択し、その戦績を競うゲームとして、八〇年代の半ばあたりから、競馬ファンの間で静かなブームとなっていた。 「今年の三歳には、エゴイストという馬がいるけど、取らなくてはいけないかな?」 「そうねえ、イッショウさんにふさわしい名前だね」 「スダホークの産駒にハクバノテンシという馬がいるけど、これが牝馬なんだからね」 「ハクバノテンニョじゃないのか?」 選択会議の前には、そんな会話が飽きることなく交わされていく。 この年は、ウイニングチケッットがダービーを、ベガが桜花賞とオークスを連覇したことから、トニービンの産駒の前評判は高く、ことにダンシングキーの息子・エアダブリンには、何人もの指名が集中すると言われていた。 まだ、一度も走ったことのない馬たちの将来を語りながら、酒の量が増えていくと、なぜか昼間に見た版画が蘇ってくる。 「ヤマニングローバルの下は、指名してはまずいんだろうな」 「だめだめ、それは指名する人は決まっている」 「ホクトビーナスの初仔は?」 「それも決まっている」 三歳馬を話題にしながらも、色彩豊かな黒の版画がいくつか浮かびあがり、すぐに消えていく。まだ見ぬ三歳馬と、昼に見た版画が交互に入り交じっていく。そのとき、だれかが近づいてくるのがわかった。 「イッショウさん。ところで今年は、どんな馬を指名しようと思っているの?」 マスターは、そういって声をかける。 頭の大きな少女の横顔を思い浮かべていた。庭園美術館で、最後に見た版画だった。頭の中は、メニエル・ノワールで真っ黒になっていたので、マスターの問いかけには答えることなく、指名リストを取り出し、手渡した。二十数頭の馬の名前が、そこには並んでいるはずだった。 マスターはそれを見ながら、うれしそうに言う。 「十一頭指名するのに、これだけで足りるの?」 「足りるでしょう」と言いながら、次第にメニエル・ノワールが薄れていく。「だいたい、シュピレヒコールなんて馬を指名する人は、僕しかいないでしょう」 「わからないよ。物好きは多いから」 「そうかなあ」と呟きながら目をやると、彼の様子が変わっていくのに気づく。 指名しようと思う馬の名前、その父馬、母馬、母の父などを、マスターが熱心に読んでいることに変わりはなかった。ただ、最初はニコニコしながら見ていたのが、いつしか眼差しは躍動を始め、嬉しそうだった表情には好奇心が浮かんでいた。 そのとき、自分がとんでもない間違いを犯してしまったたのではないか、と思った。なにか、決して他人には見せてはならないものを、見せてしまったような気になる。日記とか、手紙とか、そういう秘めておくべきものを、思わず見せてしまったのかもしれない。しかもある意味では、日記よりも手間がかかっていたし、手紙よりも秘めておくべきことは多かった。 それは、恋文だった。時間をかけ、添削を重ねた恋文だった。いわば、まだ見ぬ馬たちへ宛てた、あるいは自分のまだ見ぬこれからの一年へ宛てた、まぎれもない恋文だった。 だとするならば、秘めておくべきものではないだろう。そう思うと、見られることへの恥じらいが消えていく。思わず、六月の恋文を見ているマスターに、声をかけていた。 「今年、最初に指名する馬はね・・」と。 (初出:『1992年度・愛馬の會最終結果報告書』1993年6月) |
|||